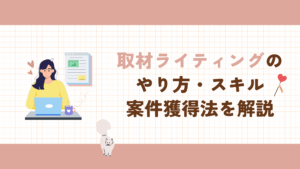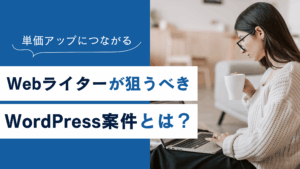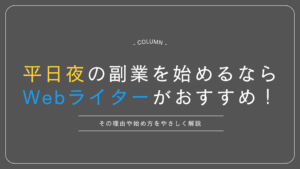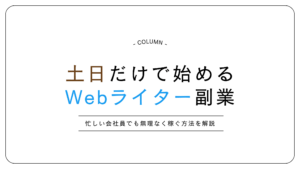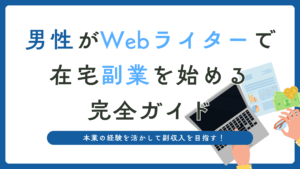「1記事書くのに何時間もかかってしまう…」「このままで副業として成り立つのかな?」と感じているWebライターの方は多いのではないでしょうか。
実は、Webライティングに時間がかかるのは誰しもが通る道です。初心者だけでなく、ある程度経験を積んだ人でも、記事の内容やジャンルによって筆が進まないことはよくあります。
納期ギリギリまで書けずに焦ってしまったり、途中で手が止まって作業が進まず、自己嫌悪に陥ったりするのもよくあることです。この記事では、Webライティングに時間がかかる原因を細かく分解し、その改善策を実践レベルで紹介します。
ライティングにかかる時間を可視化し、的確に改善を図ることで、あなたの執筆スピードは着実に向上していきます。加えて、作業効率を上げるためのツールやマインドセット、プロが実践しているテクニックも解説します。
なぜWebライティングはこんなに時間がかかるのか?
Webライティングは「ただ文章を書く仕事」ではありません。実際には、構成設計・リサーチ・文章作成・編集・SEO調整など、多くの工程が複合的に絡み合っており、それぞれに時間がかかるのが特徴です。
- 読者や検索エンジンに伝わる構成を考える
- 情報の裏付けを取るリサーチ
- SEOを意識したキーワード選定と自然な挿入
- 読みやすく自然な文章に整える編集作業
さらに、クライアントの意図に沿った内容に仕上げる必要があるため、トンマナ(トーン&マナー)の調整や事前の打ち合わせ内容の反映も求められることがあります。
特に初心者のうちは、「何を書けばいいか分からない」「書いたけど不安で直し続けてしまう」といった不安が積み重なり、想像以上に時間がかかってしまいます。また、情報の信頼性や読者目線を考えるあまり、リサーチが止まらなくなるケースもあります。
Webライティングが遅くなる代表的な5つの原因とその深掘り
次に、Webライティングが遅くなる原因5つを紹介します。
- 構成が不明確で、書きながら迷子になる
- リサーチに時間をかけすぎてしまう
- 文章表現に悩み、何度も書き直す
- 完璧主義で初稿から100点を目指してしまう
- 集中できる作業環境・時間が取れていない
それぞれ詳しく見ていきましょう。
構成が不明確で、書きながら迷子になる
構成が定まっていない状態で書き始めると、どの順番で何を書くのか迷ってしまい、途中で手が止まることが増えます。その結果、何度も書き直す羽目になり、完成までに何倍もの時間がかかります。
特に、書いている途中で「この話題、本当に必要かな?」「順番を変えたほうがいいかも」と迷ってしまうと、全体を再構築する必要が出てきてしまいます。
リサーチに時間をかけすぎてしまう
情報が足りない、信頼できるソースが見つからない…といった理由から、リサーチに何時間も費やしてしまうことがあります。
特に、医療・法律・お金といった専門性が求められるジャンルでは、信頼性のある出典を探すだけでも時間がかかります。
また、読み物系の記事でも一次情報を見つけ出すのに手間取ることが多く、リサーチの効率化は多くのライターにとっての課題です。
文章表現に悩み、何度も書き直す
「もっといい言い回しがあるかも」「なんとなく読みにくい」と感じるたびに修正を加えていると、永遠に完成しない感覚に陥ります。
ボキャブラリーや構文の引き出しが少ないと、特にこの傾向が強くなります。
また、校正スキルに自信がない場合、読み返すたびに違和感を覚え、文章を削っては書き直すの繰り返しになります。
完璧主義で初稿から100点を目指してしまう
ミスを避けよう、読みやすくしようとする意識は大切ですが、初稿の段階で完璧を求めすぎると作業が止まってしまいます。推敲段階で調整できることまで初稿で悩んでしまうと、効率が極端に落ちます。
「まずは60点で良いから書き上げる」くらいの意識が大切です。
集中できる作業環境・時間が取れていない
スマホの通知やSNS、テレビなどが視界にあると集中力が続きません。また、作業時間をきちんと確保できていないと、「時間がない中で書かなきゃ」というプレッシャーがかかり、結果として非効率になってしまいます。
家庭環境や仕事との両立、子育て中などの生活環境も執筆時間に大きく影響を与える要素です。
執筆時間を短縮するための具体策10選
次に、執筆時間を短縮する方法を10選紹介します。
- 書く前に「読者とゴール」を明確にする
- 構成を組んでから本文に取りかかる
- リサーチは「3つの情報源ルール」で効率化
- よく使う言い回し・表現をテンプレ化しておく
- タイマーを使って集中力を保つ(ポモドーロなど)
- 「初稿は荒くてOK」のマインドで書く
- 音声入力を使って下書きを一気に作る
- ChatGPTなどAIを補助的に活用する
- 書く時間をルーティン化して「脳のウォームアップ」を減らす
- 過去記事を振り返って自分の執筆ログを取る
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1. 書く前に「読者とゴール」を明確にする
記事を書く前に、ターゲットとなる読者像とその記事の目的をはっきりさせることが大切です。読者について深く考えることで、伝えたいメッセージや促したいアクションが明確になり、ブレずにスムーズに文章を書き進められるようになります。
具体的には以下のポイントを意識しましょう。
- 想定読者の属性(年齢、性別、職業、興味関心など)を明確にする
- 読者が抱えている悩みや課題を洗い出す
- 記事を通して読者に伝えたいことを明確にする
- 読者にしてほしい行動(購入、問い合わせ、シェアなど)を決める
- 記事の役割(集客、SEO対策、CVなど)を意識する
このように事前に読者像と記事の狙いを言語化しておくことで、文章の軸がぶれにくくなります。「この読者は何を知りたがっているのか」「この記事を読んで何を得られるのか」という視点を持つことが、魅力的で価値ある記事を生み出すカギとなるのです。
2. 構成を組んでから本文に取りかかる
構成を組んでから本文を書き始めることは、執筆時間を大幅に短縮するための重要なステップです。このようなメリットがあります。
- 全体像が見えやすくなる
- 手戻りが減る
- 論理的な流れを作りやすい
- アイデアが出しやすい
H2・H3レベルの見出しを作成し、各セクションに書く要点をメモしておくことで、記事の全体像を把握しやすくなります。これにより、書くべき内容が明確になり、執筆がスムーズに進みます。
また、構成を組む段階で、リサーチ結果や参照URLをまとめておけば、本文を書く際に情報を探し直す手間が省けます。必要な情報がすぐに取り出せるので、執筆に集中できます。
見出しを決めておくことで、記事の論理的な流れを事前に考えることができます。各セクションの内容が明確になるため、読者にとってわかりやすい文章を書くことができるでしょう。
さらに、見出しごとに要点をメモしておけば、本文を書く際のアイデア出しがスムーズになります。メモを見ながら、各セクションに必要な内容を思い出しやすくなるでしょう。
このように、構成を組んでから本文を書き始めることは、執筆時間の短縮につながります。全体像を把握し、論理的な流れを作ることで、読者にとってわかりやすい文章を効率的に書くことができるのです。ぜひ、執筆前の構成作りを習慣づけてみてください。
3. リサーチは「3つの情報源ルール」で効率化
リサーチを効率的に行うには、情報源を「3つ」に絞るのがおすすめです。例えば、以下のような信頼性の高いソースに絞ることで、情報の正確性を担保しつつ、探し続ける時間を大幅にカットできます。
- 公的機関のサイト
- 大手メディア
- 業界の専門家のブログ
また、Google検索のテクニックを使いこなすことで、さらなる時短が可能です。特に以下の検索演算子を活用すると、目的の情報により素早くたどり着けるでしょう。
- site: 特定のサイトやドメインを検索
- intitle: タイトルに特定のキーワードを含むページを検索
- filetype: 特定のファイル形式(PDF、Wordなど)を検索
情報収集は際限なく続けられてしまうものですが、上限を設けることで、リサーチ時間を適切にコントロールできます。信頼できる3つの情報源を決めて、検索テクニックを駆使しながら効率的に情報を集めましょう。
そうすることで、質の高い記事を短時間で執筆することが可能になるはずです。

4. よく使う言い回し・表現をテンプレ化しておく
よく使う言い回しや表現をテンプレート化しておくのは、記事執筆の時間短縮に効果的です。特に以下のようなパターン化しやすい部分をストックしておくと便利でしょう。
- 記事の導入文やまとめの文章
- SEO対策で頻繁に使うフレーズ
- 見出しの前後につなぐ定型文
- 画像の説明文
- CTA(読者アクション喚起)の文言
自分なりの「記事パーツ辞書」をExcelなどで作成しておけば、文章を一から考える手間が省けます。使い回しによる文体のブレも防げるので一石二鳥です。
執筆中、適切なテンプレートをサッと参照できるよう、見やすい形式で管理するのがポイント。カテゴリー分けしたり、キーワードで検索できる仕組みを用意しておくと活用しやすくなります。
記事作成の合間にテンプレートを追加・更新していけば、どんどん使えるストックが増えていきますよ。
5. タイマーを使って集中力を保つ(ポモドーロなど)
タイマーを使って作業を区切ることは、集中力を保ち、執筆時間を短縮するのに効果的です。特に、集中力が途切れがちなライターにおすすめなのが、ポモドーロ・テクニックです。
このテクニックは以下のようなサイクルを繰り返します。
- 25分間集中して作業する
- 5分間休憩を取る
- 4セット(約2時間)終えたら、少し長めの休憩を取る
25分という短い時間設定により、集中力を最大限に発揮しやすくなります。また、休憩時間を設けることで、頭をリフレッシュでき、次のセットに向けて気持ちを切り替えられます。
ポモドーロ・テクニックを実践するのに便利なのが、Google Chromeの拡張機能やスマホアプリです。タイマーの設定から管理まで、すべて自動で行ってくれるので、ライターは執筆に専念できます。
時間を区切って集中することで、ダラダラ書きがちな人でも、効率的に文章を完成させられるでしょう。ぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。
執筆時間の短縮につながるはずです。
6. 「初稿は荒くてOK」のマインドで書く
最初から完璧な文章を書こうとすると、かえって時間がかかってしまうものです。初稿の段階では、文章の細部にこだわらず、とにかく思いついたことを書き出していくことが大切です。
初稿を書き上げたら、改めて見直して推敲を重ねていけばいいのです。このように割り切ることで、執筆中に立ち止まってしまう時間を減らすことができます。具体的には、以下のようなマインドを持つとスムーズに書けるでしょう。
- 最初は荒くても構わない。あとでブラッシュアップすればいい
- 思いついたことをどんどん書き出そう。取捨選択は後回しだ
- 書きながら推敲していては先に進めない。まずは書ききることが大事
「とにかく最後まで書ききる」ということを意識するだけで、執筆への心理的ハードルは下がります。書き上げてから見直せば、意外とまとまった文章になっているはずです。あとは推敲を重ねて、少しずつ洗練させていけば完成です。
7. 音声入力を使って下書きを一気に作る
音声入力を活用すれば、アイデアを素早く文章化できます。話すのが得意な人にとって、音声入力は執筆時間を大幅に短縮するための強力なツールとなるでしょう。
音声入力のメリットは以下の通りです。
- スマホやPCに標準搭載されているものが多く、無料で使える
- 口語調の記事を書く際に、自然な言い回しが出やすい
- キーボードで文字を打つよりも速く入力できる
- 書くことへの抵抗感が少なく、アイデア出しがスムーズ
特に、ブログ記事やSNSでの発信など、くだけた文体が求められるシーンでは音声入力との相性が抜群です。書くことが苦手な人でも、話し言葉でアイデアを形にしていくことができるでしょう。
まずは音声入力を使って下書きを作り、それをベースに推敲していくのがおすすめの使い方です。思いついたアイデアを即座に言語化できるので、執筆のファーストステップとして活用してみてください。
普段はキーボードで文章を打ち込んでいる人も、音声入力を取り入れることで執筆の効率化が図れるはずです。
8. ChatGPTなどAIを補助的に活用する
ChatGPTなどのAIツールを執筆の補助として活用することで、作業効率を大幅に高めることができます。ただし、AIが出力したテキストをそのまま使うのは避けましょう。あくまでもアイデア出しや思考の整理に役立てるのが賢明な使い方です。
具体的な活用方法としては以下のようなものが挙げられます。
- 記事の構成案やアウトラインの作成
- 書き出しや結びの文章案の生成
- 言い換え表現や類語の提案
- 文章のトーンや語彙のチェック
- 文章の校正や推敲のサポート
AIツールに頼りすぎるのは禁物ですが、適切に活用することで執筆のスピードアップにつながります。書き手の思考を補完し、創造性を刺激するパートナーとして、AIを上手に取り入れていきましょう。
最終的には自分の言葉で洗練させることを忘れずに、執筆プロセスの効率化を図ることが大切です。
9. 書く時間をルーティン化して「脳のウォームアップ」を減らす
毎日決まった時間に書くことを習慣づけると、脳が自然と「書くモード」に切り替わるようになります。これにより、本格的な執筆に入る前のウォーミングアップ時間を大幅に短縮できるのです。
朝の出勤前、昼食後、夜の静かな時間帯など、自分に合ったベストな執筆タイミングを見つけることがポイントです。そのタイミングを毎日繰り返すことで、脳が執筆に最適な状態になっていきます。
短時間でも集中して書けるようになるので、忙しい中でも確実に執筆時間を確保しやすくなるでしょう。執筆のルーティンを確立して、効率的に文章を書き上げる習慣を身につけましょう。
10. 過去記事を振り返って自分の執筆ログを取る
自分の執筆ログを取ることは、時間の使い方を見直すうえでとても効果的です。記事を書く際にどの工程でどれくらい時間を使ったのかを記録することで、自分の執筆パターンが可視化されます。
具体的には、以下のような項目を記録するとよいでしょう。
- リサーチに費やした時間
- 記事の構成を考えるのにかかった時間
- 実際の執筆にかかった時間
- 推敲や校正に使った時間
これらを記録していくことで、自分が時間を使いすぎている部分が明らかになります。そうすれば、その部分を重点的に改善することで、執筆の効率化につなげられるというわけです。
記録をつけるツールとしては、ExcelやGoogleスプレッドシートなどの表計算ソフトがおすすめです。表形式で記録をつけることで、時間の使い方の傾向が一目で把握できます。
最近ではNotionなどのオールインワンツールも人気で、タスク管理と一元化して記録を残せる点が魅力です。
自分に合ったツールを使って執筆ログをつけることで、ムダな時間を削り、生産性を高めていきましょう。改善を重ねるたびに、執筆時間の短縮につながっていくはずです。
それでも時間がかかるときの対処法|案件や働き方の見直しも視野に
ここまで紹介した原因や対策だけでは解決できないときもあります。ここでは、色々な方法を試した方に向けて、時間がかかるときの対処法を紹介します。
▼こちらもチェック

「短納期・大量執筆」が合っていない可能性もある
ウェブライターとして案件を受ける際、1記事あたりの単価や納期は重要な判断材料になります。特に、短い納期で大量の原稿を求められる案件は、高収入を得るチャンスのように思えるかもしれません。
しかし、自分のライティングスタイルや作業ペースによっては、このタイプの案件が必ずしも適しているとは限りません。以下のような場合は、「短納期・大量執筆」の案件が自分に合っていない可能性があります。
- 1記事に時間をかけてじっくり取り組みたい
- 情報の収集や構成を入念に行いたい
- 推敲を重ねて質の高い原稿を目指したい
このようなスタイルで執筆したい場合、短い納期でたくさんの本数をこなすことは難しく、ストレスを感じてしまうかもしれません。むしろ、本数を減らして1記事あたりの単価を上げる方向にシフトするのも一つの選択肢です。
自分に合ったペースでクオリティの高い原稿を書くことが、長期的には評価につながり、安定した収入を得られる可能性があります。
ウェブライターとして成功するには、自分に合った働き方を見つけ、ストレスを最小限に抑えながら力を発揮できる環境を整えることが大切です。
自分の得意ジャンルを見つけてリサーチ時間を削減
自分の得意ジャンルを見つけることは、ライティング時間を大幅に短縮できる効果的な方法です。得意な分野であれば、リサーチに費やす時間を最小限に抑えられるため、全体的な作業時間を大きく削減できるでしょう。
得意ジャンルのライティングには以下のようなメリットがあります。
- リサーチ時間を大幅に短縮でき、効率的に記事を量産できる
- 専門性が高まるため、実績を積みやすく単価アップにつながりやすい
- 継続案件を獲得しやすく、安定した仕事量を確保できる
- 好きなジャンルであれば、モチベーションを維持しながら長期的に取り組める
まずは自分の知識や経験、興味関心が高い分野を洗い出してみましょう。それらの中から、需要が高くライティング案件の多いジャンルを選ぶのがおすすめです。そうすることで、得意分野を活かしつつ、安定した仕事を獲得しやすくなります。
ジャンルを絞ることで専門性が高まれば、他のライターとの差別化を図ることもできるでしょう。高品質な記事を安定して納品できると評価が上がり、より良い条件の案件も獲得しやすくなります。
もちろん、最初から完璧な記事を書く必要はありません。得意ジャンルであっても、実際に記事を書いていくことで徐々にスキルは向上していきます。
まずは興味のある分野から始めて、経験を積みながら得意分野を確立していくのが良いでしょう。
報酬と時間を見直して「時給単価」を改善
報酬と時間を見直して「時給単価」を改善
ライターとして記事を書く際、1記事あたりの報酬に注目しがちですが、それだけでは仕事の効率性を正しく判断できません。報酬だけでなく、記事の作成にかかる時間も意識することで、「時給」という観点から案件を見直すことができるのです。
例えば、以下のようなケースを考えてみましょう。
- 1記事8,000円の案件だが、1記事につき6時間かかる場合、時給は約1,300円
- 1記事4,000円の案件だが、1時間で書ける場合、時給は4,000円
このように報酬と作業時間を数値化してみると、自分にとって本当に効率のよい案件が見えてきます。時給単価を意識することで、より収入アップにつながる働き方の選択ができるでしょう。
もちろん、単価の高い案件ばかりを選べるわけではありません。案件の内容や自分のスキルに合わせて、バランスを取ることも大切です。ただ、時給を意識するクセをつけることで、全体的に効率のよい仕事の仕方を目指せるはずです。
ライターの仕事で収入を上げるには、報酬額だけでなく時間の使い方にも目を向けることが重要だといえるでしょう。時給単価を改善する努力を重ねることで、自分に合ったベストな働き方を見つけていってください。
執筆時間の記録を取って、自分なりの改善サイクルを作ろう
執筆に時間がかかると感じるライターは多いでしょう。その場合、まずは執筆時間の記録を取ることから始めてみましょう。執筆プロセスを以下のように項目ごとに分けて、それぞれにかかった時間をログに残します。
- 構成:30分〜60分
- リサーチ:60分〜90分
- 執筆:90分〜120分
- 推敲・編集:30分〜60分
このように記録をつけることで、どの作業に時間がかかっているのかが明確になります。時間の使い方を意識するようになれば、少しずつ無駄な作業に気づき、効率化のヒントが見えてくるはずです。
また、時間ログを取ることには別のメリットもあります。他のライターとの比較や、自分の過去の記録との比較によって、スキルアップの度合いを実感できるのです。
数字として目に見える形で成長を確認できれば、さらなる上達へのモチベーションにつながるでしょう。
執筆時間を短縮するコツをいきなり見つけるのは難しいかもしれません。しかし、自分の作業プロセスと向き合い、地道にログを取る習慣をつけることが、着実な成長への第一歩となります。
ぜひ、時間記録から始めて、自分なりの改善サイクルを作っていきましょう。
まとめ:スピードは「経験×工夫」で必ず伸びる
Webライティングに時間がかかるのは、誰にでもあることです。しかし、原因を明確にし、具体的な改善策を試すことで、少しずつスピードアップすることができます。
「自分は遅いからダメだ」と落ち込むのではなく、「伸びしろがある」と前向きにとらえましょう。経験を積みながら、自分に合った工夫を積み重ねていくことで、質とスピードの両立ができるようになります。
今日できる小さな工夫から始めて、着実に成長を重ねていきましょう。