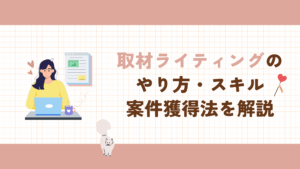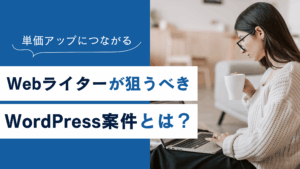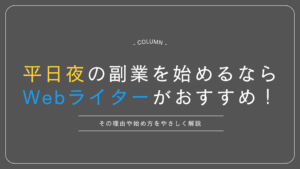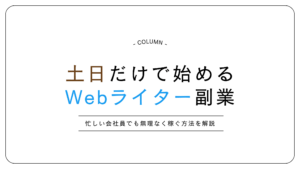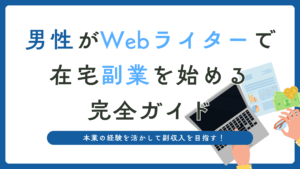リサーチに「時間がかかりすぎる」「正しいやり方がわからない」「集めた情報が合っているか不安」といった悩みを抱えていませんか? リサーチ不足は、記事の信頼性を損ね、読者からの低評価やリライトの手間につながる大きな原因となります。
本記事では、Webライターにとってなぜリサーチが重要なのかを解説するとともに、初心者でも迷わない具体的なリサーチ手順や、情報収集を効率化する便利なツールを詳しく紹介します。
この記事を最後までお読みいただければ、正確かつスピーディーなリサーチが可能になり、自信を持って質の高い記事を書けるようになります。リサーチ力を高めて、他のWebライターと差をつけたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
Webライターにおけるリサーチの重要性
まずは、リサーチの重要性について見ていきましょう。
リサーチ不足が記事に与える悪影響
リサーチ不足が記事に与える悪影響は、想像以上に大きなものです。十分なリサーチをせずに記事を書いてしまうと、以下のようなリスクが生じる可能性があります。
- 誤情報や読者のニーズとズレた内容になる
- 検索上位に上がることが難しくなる
- 読者からの信頼を得にくくなる
- ライターとしての信頼性が損なわれる
- 読者にとって役に立たない記事だと判断され、すぐに離脱される
- サイト全体の評価が下がる要因になる
たとえば、「副業Webライターの始め方」というテーマで記事を書く際、クラウドソーシングの存在や現場での実際の業務フローを知らずに執筆してしまうと、現実と乖離した内容になってしまうでしょう。そうなれば、読者にとって実用性のない記事となり、信頼を失うことにつながります。
また、誤った情報を掲載してしまうことで、ライターとしての信頼性が大きく損なわれるリスクもあります。読者は正確で信頼できる情報を求めているため、不正確な記事は敬遠されてしまうのです。
リサーチ不足による悪影響を避けるためには、執筆前に十分な情報収集と検証を行うことが不可欠です。信頼できる情報源から得た正確な情報をもとに、読者のニーズに合致した有益な記事を提供することが、Webライターに求められる重要なスキルなのです。
情報の正確性が信頼と評価につながる
情報の正確性は、Webライターにとって極めて重要な要素です。読者は信頼できる情報を求めており、その期待に応えることがライターの責務と言えるでしょう。
例えば、「青色申告の特典」について説明する記事を考えてみましょう。この場合、情報ソースとして次の2つのアプローチが考えられます。
- 国税庁の公式サイトなど、一次情報源をもとに記事を執筆する
- 他の記事からの引用を繋ぎ合わせ、二次的な情報で記事を構成する
前者のように確かな情報源に基づいた記事は、読者に信頼感を与えます。一方、後者のような曖昧な情報ソースに頼った記事では、読者の印象は大きく異なるでしょう。
正確な情報を提供することは、読者からの信頼獲得に直結します。そしてその信頼は、SNSでのシェアやブックマークといった二次的な評価にもつながっていきます。
また、SEOの観点からも、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)が重視される昨今、適切なリサーチは欠かせないスキルと言えるでしょう。
情報の正確性を担保するためには、信頼できる一次情報源を確認し、情報を精査することが肝要です。Webライターにとって、リサーチ能力は必須のスキルなのです。
リサーチの基本ステップ|初心者でも迷わない流れ(執筆段階編)
ここからは記事の見出し構成がある前提で、執筆時にリサーチする具体的な手順を解説します。具体的な流れは、以下の5ステップです。
- 見出しごとの「検索意図」を読み解く
- 見出しのキーワードで実際に検索して、競合記事を確認する
- Q&AサイトやSNSでリアルな声を探す
- 信頼できるデータや一次情報がないか探す
- 集めた情報をもとに「伝えるべき要素」を整理する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
ステップ1:見出しごとの「検索意図」を読み解く
見出しごとの検索意図を読み解くことが、質の高い記事を書くための第一歩です。読者の立場に立って、その見出しを見たときにどんな疑問や関心事を持つかを考えることが重要です。
例えば、「Webライターのメリット」というh2見出しの下に「手軽で始めやすい」というh3見出しがあったとします。この場合、読者の頭には以下のような疑問が浮かぶはずです。
- 未経験でもWebライターを始められるのはなぜか
- どのくらいの準備があれば始められるのか
- 他の副業と比べてWebライターはどれほど楽なのか
このように、見出しから読者の疑問点を想像し、その答えとなる情報をリサーチして記事に盛り込むことが求められます。読者目線で考えることで、より満足度の高い記事を作ることができるのです。
見出しの検索意図を読み解くコツをまとめると、以下のようになります。
- 自分が読者だったらどんなことが気になるか考える
- 見出しに関連する疑問を複数挙げてみる
- 挙げた疑問に対する答えを探すようにリサーチする
- 見出しの内容を十分に説明できる情報を集める
読者目線に立って見出しを分析し、求められている情報を的確に提供することが、良質な記事を生み出すカギとなります。検索意図を意識したリサーチと執筆を心がけましょう。
ステップ2:見出しのキーワードで実際に検索して、競合記事を確認する
見出しのキーワードを実際に検索エンジンで調べて、上位に表示される競合記事をチェックするのは重要なステップです。ここでは、読者が知りたがっている情報や、よく使われている表現、伝え方などを把握することができます。
具体的には以下のようなポイントに注目しましょう。
- 記事の構成や見出しの付け方
- 読者の疑問や悩みに対する答え方
- 具体的な数字やデータの使い方
- 図表やイラストなどビジュアル要素の活用法
- 読者に安心感を与えるような表現
- 記事の文体や語彙のレベル
これらの点を分析することで、自分の記事に足りない部分や、差別化できるポイントが見えてきます。
たとえば、Webライターに関する記事であれば、「初期投資が少ない」「パソコン1台で始められる」「未経験でもOK」といった共通点が見られるかもしれません。これは、多くの読者が気になるポイントだと言えます。
ここで重要なのは、ただ真似をするのではなく、競合記事にはない切り口や情報を加えること。読者にとって、他にはない価値のある記事を作ることが求められます。
自分なりのオリジナリティを出すことを意識しながら、競合分析の結果を活かしていきましょう。
ステップ3:Q&AサイトやSNSでリアルな声を探す
Webライターとして活動していく上で、検索エンジンからの情報収集は欠かせません。しかし、それだけでは物足りないこともあるでしょう。より実践的で生の声を知るために、Q&AサイトやSNSを活用してみましょう。
Yahoo!知恵袋や教えて!gooなどのQ&Aサイトでは、「webライター 始め方」「未経験 ライター 難しい」といった検索ワードで調べることで、実際にライターとして活動を始めた人たちが抱える疑問や悩みを知ることができます。
そこから見えてくるのは、初心者ならではの生の声です。
また、X(旧Twitter)上で「#Webライター初心者」「#ライター副業」などのハッシュタグを検索すれば、ライターとして活動する人たちの実体験やリアルな声を見つけられます。
喜びや驚き、悩みや課題など、ありのままの思いが投稿されていることでしょう。
こうした一次情報としての生の声は、記事に説得力や共感を呼ぶ要素を加えてくれます。読者に「自分と同じ悩みを抱えている人がいる」「実際にライターとして活躍している人の体験談だ」と感じてもらえれば、記事への信頼も高まるはずです。
Q&AサイトやSNSでの情報収集を通じて、読者の立場に立った記事作りを心がけましょう。そこで得られた生の声を記事に反映させることが、魅力的なコンテンツ作りへとつながっていきます。
ステップ4:信頼できるデータや一次情報がないか探す
記事の質を大きく左右するのが、具体的な数字や一次情報の有無です。たとえば、「クラウドワークスの登録者数は2024年時点で450万人を超える」といった具体的なデータを盛り込むことで、記事の信頼性や説得力が格段に高まります。
このようなデータを見つけるには、以下のような方法があります。
- 企業の公式発表を探す
- 調査レポートを活用する
- 官公庁の統計を調べる
- 大学の研究成果を参考にする
企業の公式発表を探す際は、「クラウドソーシング 登録者数」「Webライター 平均報酬」などのキーワードで検索すれば、クラウドワークスやランサーズといった企業の公式発表にたどり着けることがあります。
また、民間のシンクタンクや調査会社が実施した調査レポートにも、役立つデータが含まれていることがあります。総務省の統計データなど、政府機関が公表している統計にも目を通しておくと良いでしょう。
さらに、大学の研究機関が発表している論文やレポートにも、専門的な知見が詰まっています。
もちろん、一次情報を見つけられないこともありますが、できる限り信頼できるデータを盛り込むよう心がけましょう。具体的な数字を示すことで、読者に「なるほど」と納得してもらえる記事になるはずです。
ステップ5:集めた情報をもとに「伝えるべき要素」を整理する
リサーチを進めていく中で、集めた情報をもとに「伝えるべき要素」を整理することが大切です。
情報を読者にとって最も理解しやすい順番で並べ替え、1つ1つの要素に具体例や数字、実体験を加えることで、読者に「なるほど、これは本当に自分でもできそうだ」と思ってもらえるような内容になります。
例えば、「Webライターは始めやすい」という要素について伝える場合は、以下のように整理するとよいでしょう。
- 初期コストが低い
- 必要な道具はパソコンのみ
- 登録先が豊富にある
- 未経験OKの案件が多数ある
- すぐに仕事が見つかる
これらの具体的なポイントを、実際の数字や事例を交えて説明することで、読者にとって説得力のある内容になります。
また、情報を整理する際は、読者の理解度や関心に合わせて、論理的な流れを意識することも重要です。
例えば、Webライターとして始める方法を説明する場合、まずは始めやすさをアピールし、次に具体的な始め方のステップを示すといった順番で情報を並べると、スムーズに内容を理解してもらえるでしょう。
このように、集めた情報を読者目線で整理し、分かりやすく伝えることを心がけましょう。読者にとって価値のある情報を、魅力的に発信できるはずです。
Webライターが使えるおすすめリサーチツール
次に、Webライターがリサーチする際に活用できるツールと、その活用法について解説します。
Google検索+検索演算子の活用法
Google検索は、Webライターにとって強力なリサーチツールの1つです。単純にキーワードを入力するだけでなく、検索演算子を活用することで、より効率的に必要な情報を見つけることができます。
検索演算子の使い方は以下の通りです。
| 検索方法 | 説明 |
|---|---|
| AND検索 | 複数のキーワードをANDで繋ぐことで、両方の単語を含むページのみを検索結果に表示 |
| OR検索 | 複数のキーワードをORで繋ぐと、いずれかの単語を含むページが検索結果に表示 |
| 特定のサイト内検索 | 「site:ドメイン名 キーワード」の形式で入力すると、指定したドメイン内からキーワードを検索 |
例えば、「”Webライター” AND “未経験”」と入力すると、WebライターとWebライターの両方の単語を含むページが見つかります。また、「site:gov.jp 青色申告」と入力すれば、gov.jpドメイン内から青色申告に関するページを探し出せます。
検索結果のページタイトルとスニペット(ページの説明文)をよく読むことで、目的の情報を素早く見つけることができるでしょう。AND検索、OR検索、サイト内検索などの演算子を使いこなせば、Webライターに必要な情報収集の効率が大幅に上がるはずです。検索のコツを身につけて、質の高い記事作成に役立ててください。
Q&Aサイト(Yahoo!知恵袋など)の使い方
Yahoo!知恵袋やOKWave、教えて!gooなどのQ&Aサイトは、Webライターにとって大変便利なリサーチツールです。これらのサイトでは、一般ユーザーから寄せられた生の疑問や悩みを見ることができます。
例えば、ライティング初心者であれば以下のようなキーワードで検索してみましょう。
- クラウドワークス 稼げない
- 初心者 ライティング 続かない
- Webライター 挫折
すると、実際に仕事を始めたばかりのライターが感じている悩みが、リアルな言葉で書かれています。これらの生の声を記事内で拾い上げることで、読者に寄り添ったコンテンツ作りが可能になります。
また、Q&Aサイトの情報は以下の点で役立ちます。
- 読者の関心が高いトピックがわかる
- 記事に盛り込むべき具体的な内容のヒントが得られる
- 読者の知識レベルや理解度を把握できる
ただし、Q&Aサイトの情報をそのまま鵜呑みにするのは禁物です。情報の正確性については自分でもしっかり確認し、信頼できるソースから裏付けを取ることが重要です。
うまく活用すれば、Q&Aサイトは記事の質を高めるための強力な味方となるでしょう。
SNS・X(旧Twitter)でトレンドを探す
SNSやXを活用して、Webライターに役立つトレンド情報を収集しましょう。特に「#Webライター」「#ライター仲間募集中」などのハッシュタグで検索すると、多くの経験者が日々の活動や失敗談、成功体験をシェアしています。これらの情報から、以下のようなことが分かります。
- 今何が話題になっているのか
- どんな案件が流行しているのか
- ライターが何に困っているのか
SNSでは、リアルタイムで語られる生の声を拾うことができるので、読者のニーズをダイレクトに感じ取れます。
例えば、あるベテランライターが「最近はAIに関する記事の需要が高い」とつぶやいていれば、そういった分野の記事を書くことで、より多くの人に読んでもらえる可能性が高くなります。
また、ライター仲間の失敗談から学ぶことも多いでしょう。「あの時こうしておけば良かった」という後悔の言葉からは、同じ轍を踏まないためのヒントが隠れています。
SNSの情報を参考にすることで、旬のテーマを取り入れた読者ニーズに近い記事を作成できるはずです。普段からアンテナを張って、トレンドの移り変わりをウォッチしておくことが大切ですね。
競合記事の読み込みと差別化のヒント
競合記事を丁寧に読み込むことは、自分の記事の質を高めるために非常に重要です。上位にランクインしている記事は、Googleが高く評価している内容であるため、参考になる部分がたくさんあるはずです。
競合記事から学べるポイントとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 見出しの構成や順番
- 導入部分の書き方や語り口
- 記事全体の情報量や密度
- 画像や動画などのメディアの使い方
- 読者を引き付けるデザインのテクニック
これらの要素を詳しく分析し、自分の記事に取り入れられる部分はどんどん活用していきましょう。一方で、ただ真似をするだけでは他の記事と差別化できません。競合記事にはない独自の価値を提供することが重要です。
差別化を図るためのアイデアとしては、次のような方法が考えられます。
- 自分だけが持っている体験談を盛り込む
- 独自のデータ調査を行って、オリジナルの情報を提示する
- 読者の共感を呼ぶような視点から記事を書く
競合記事の良い部分は吸収しつつ、自分にしかできない切り口を見つけることで、他にはない魅力的な記事を作り上げていきましょう。
AIを活用した情報収集(ChatGPT・Geminiなど)
AIを活用したリサーチツールは、Webライターの情報収集を大幅に効率化してくれます。ChatGPTやGeminiなどのAIは、情報整理や構成案作成、調べるべき切り口の提示など、さまざまな場面で役立ちます。
たとえば、「Webライターのメリットを5つ挙げてください」とAIに尋ねれば、執筆に必要なポイントを簡潔にリストアップしてくれます。
また、曖昧な見出しに対して「この見出しには何を含めるべきか」と相談することで、調査方針を明確にすることもできます。
AIのWebリサーチ機能を使えば、情報収集をスピーディーに行うことが可能です。サービスの比較などを行う際は、Deep Researchを活用することで効率的にデータを集められるでしょう。
ただし、AIから得られる情報はあくまで補助的なものであることを忘れてはいけません。一次情報として使う際は、必ず信頼できる出典で裏付けを取るようにしましょう。AIを使ったリサーチ後のチェックは欠かせません。
適切に活用すれば、AIはWebライターにとって強力な味方となるはずです。情報収集の効率を高め、質の高い記事作成につなげていきましょう。
リサーチがうまくいかない時の対処法
リサーチの経験が浅いと、なかなかうまくリサーチできないこともあります。ここでは、うまくいかないときの対処法を3つ紹介します。
- 検索ワードを変える
- 英語検索+翻訳を試してみる
- AIツールを活用してヒントを探す
それぞれ詳しく見ていきましょう。
検索ワードを変える
リサーチの際に思うような情報が見つからず、行き詰まってしまうことは誰にでもあります。そんな時は、検索ワードを変えるテクニックを活用してみましょう。
検索ワードを変更する際のコツは以下の通りです。
| テクニック | 説明 |
|---|---|
| 言葉を言い換える | 例えば「Webライター 始め方」でヒットしないなら、「副業 ライティング 入門」「ライティング 仕事 初心者」などに変更する |
| 視点を変える | 「とは」「コツ」「事例」などのワードを加えることで、解説系や体験談系の記事が見つかりやすくなる |
| 関連キーワードを追加する | メインキーワードに加えて、関連性の高いキーワードを組み合わせる |
| 検索エンジンを変える | GoogleだけでなくYahoo!やBingなど、複数の検索エンジンを活用する |
検索ワードを工夫することで、これまでとは異なる情報に出会えるはずです。様々なアプローチを試してみて、リサーチの幅を広げていきましょう。
行き詰まったと感じた時こそ、発想の転換のチャンスです。柔軟な思考でリサーチに取り組むことが、良質なコンテンツ作りにつながっていくのです。
英語検索+翻訳を試してみる
英語で検索してみる 日本語で情報が見つからない場合は、英語で検索してみるのも一つの手です。例えば、フリーランスライターとして活動を始める方法を探すなら、「freelance writing how to start」などのキーワードで検索してみましょう。
英語圏のサイトでは、日本にはないようなノウハウや調査データが見つかるかもしれません。新しい視点やアイデアのヒントが得られる可能性が高いのです。
英語が苦手でも大丈夫。最近の翻訳ツールは非常に優秀で、Google翻訳やDeepLなどを使えば、たいていの英語記事は問題なく理解できます。翻訳ツールを活用すれば、英語力に自信がない人でも、十分にリサーチが可能なのです。
英語圏の情報を取り入れることで、日本語だけでは得られない発見があるはずです。言葉の壁を越えて、グローバルな視野でリサーチ力を高めていきましょう。
AIツールを活用してヒントを探す
リサーチが行き詰まった時は、AIツールを活用してみるのも一つの手です。例えば、ChatGPTなどのAIチャットボットに、以下のようなことを質問してみましょう。
- この見出しではどのような内容を書くべきだと思いますか?
- 検索意図を考えると、他にどのような要素を盛り込むべきでしょうか?
- この見出しに対して、具体的にどのようなアプローチで書けば良いでしょうか?
AIは膨大なデータを学習しているため、意外な観点やアイデアを提示してくれることがあります。時には自分では気づかなかった盲点を指摘してくれるかもしれません。
もちろん、AIの提案をそのまま鵜呑みにするのではなく、最終的には自分の頭で考えることが大切です。しかし、行き詰まった時の壁打ち相手としてAIを活用し、思考の幅を広げるのは非常に有効な方法と言えるでしょう。
AIからのフィードバックを参考にしつつ、自分なりのアイデアを膨らませていきましょう。そうすることで、リサーチの行き詰まりを突破し、より良い記事を作成できるはずです。
記事執筆を効率化したい方によくある悩みとその回答
リサーチに限らず、執筆時間で悩んでいる人はとても多いです。ここでは、記事執筆を効率化したい方によくある3つの悩みとその回答を紹介します。
- 文章が書けず手が止まったときはどうすればいい?
- 執筆に時間がかかるときの対処法は?
- 執筆の効率化につながるツールはある?
それぞれ詳しく見ていきましょう。
▼こちらもチェック
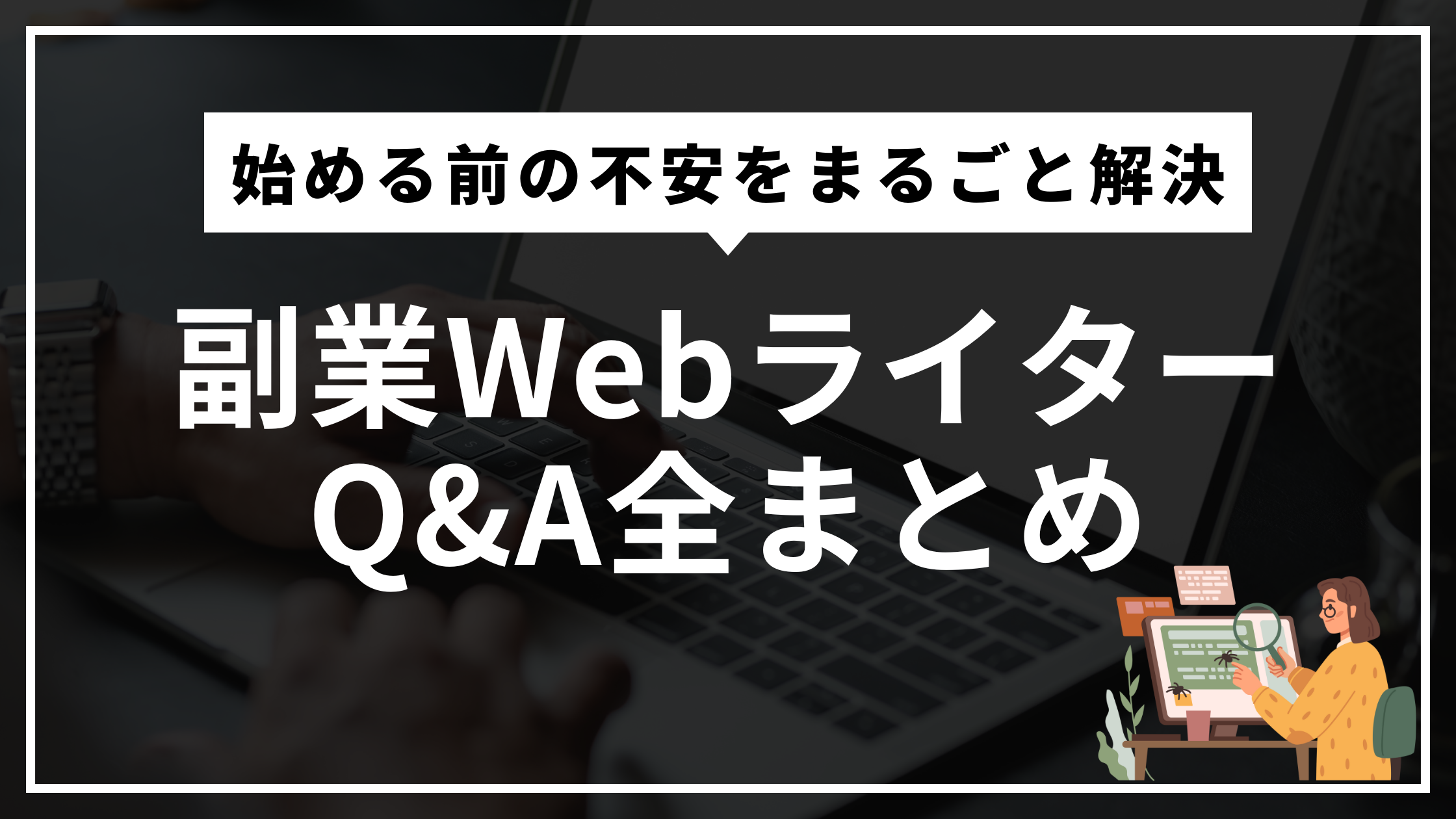
文章が書けず手が止まったときはどうすればいい?
文章が書けず行き詰まったときは、以下の方法を試してみるのがおすすめです。
まず、書きたいテーマについて頭の中で自由に思いついたことを書き出してみましょう。考えを言葉にすることで、アイデアが整理され、書き出すきっかけになります。
次に、書く内容の全体像を掴むために、アウトラインを作成してみるのも効果的です。全体の構成が明確になれば、書く順番が見えてきて、スムーズに進められるようになるでしょう。
さらに、一度書いた文章を読み返して推敲することも大切です。推敲を繰り返すことで、文章が洗練され、執筆のペースがつかめるようになります。
なお、手が止まったときの対処法は以下の記事でも詳しく解説しています。あわせてご一読ください。

執筆に時間がかかるときの対処法は?
執筆に時間がかかってしまうときは、自分に合ったリズムをつかむことが重要です。集中力が続く時間帯を見つけて、その時間を執筆に充てるようにしましょう。
また、1回の執筆時間を短めに区切って、こまめに休憩を取り入れるのも効果的です。集中力を長く維持できるようになります。
加えて、執筆前に調べ物や資料集めを済ませておくことも時間節約につながります。執筆中に調べ物をするのは、時間のロスになりがちなのでご注意ください。
なお、執筆時間がかかるときの対処法は以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご一読ください。

執筆の効率化につながるツールはある?
執筆の効率化には、便利なツールを活用するのがおすすめです。アウトラインの作成におすすめなのが、マインドマップ作成アプリです。
全体像を視覚的に捉えられるので、構成を練りやすくなるでしょう。また、文章作成アプリの校正機能を使えば、スペルミスや文法の誤りを指摘してくれるので時間を節約できます。
さらに、タイピングが苦手な人は音声入力アプリの利用がおすすめです。話すことで文章を組み立てられるので、スピードアップが期待できます。
ライティングのお悩みは、工夫次第で解消することができます。自分に合った方法を見つけて、執筆を効率化していきましょう。
まとめ:リサーチ力がWebライターの差になる
本記事では、Webライターが抱えがちなリサーチの悩みに対し、その重要性から具体的な手順、効率化ツール、そして行き詰まった時の対処法までを詳しく解説しました。
リサーチは単なる情報収集ではなく、記事の信頼性を高め、読者からの信頼を得て、ひいてはWebライターとしての評価を確立するための土台となるものです。
検索意図の把握から競合分析、一次情報や読者の生の声まで、多角的な視点から情報を集め、整理する力が求められます。
Google検索演算子やQ&Aサイト、SNS、AIツールなどを賢く活用することで、リサーチ作業は格段に効率化できます。また、もしリサーチで壁にぶつかっても、検索ワードの変更や英語検索、AIへの相談など、様々な打開策があることをご紹介しました。
リサーチ力は、Webライターとしての実力を測る重要な指標の一つです。本記事を通じて、正確かつ効率的なリサーチのノウハウを習得し、ぜひ今日から実践してみてください。
あなたのリサーチ力が向上することで、他のWebライターとの差をつけ、より質の高い記事を生み出すことができるはずです。リサーチを味方につけて、自信を持ってライティングに取り組みましょう。